共栄ニュース 6月号「乗務員の配置転換」
2024/06/03
Y社は配送業務と構内入出荷業務を行っています。配送部門は乗務員の定着率が良いものの、構内作業部門は離職率が高く、慢性的に人手不足に悩まされています。
先日、A乗務員が朝のアルコールチェックに引っ掛かり当日乗務ができなくなりました。A乗務員は過去にもしばしば同様のケースがあり、配車担当者の悩みの種でもありました。そのため社内から「Aさんを構内業務に配置転換してほしい」との要望があり、会社側もそれを受け入れました。ところがAさんはその配置転換命令を拒否しました。理由は、入社時に乗務員として採用され他の業務への異動の可能性は説明されていないし、構内作業部門に異動すれば給料が大幅に下がるからということでした。Aさんの言い分は認められるのでしょうか?
今年の4月以降新たに雇用契約を結ぶ場合は、有期契約、無期契約を問わず契約書に「業務の内容」「就業の場所」について将来的に変更の可能性があればその旨、記載することを義務付けました。
Aさんは数年前に入社し、入社時に交わした雇用契約書には業務内容の変更の可能性については特に定めはありませんでした。Aさん自身も、乗務員以外の仕事に関わることは一切想定していませんでした。
乗務員として採用されたAさんの配置転換命令の可否を判断するための参考となる最高裁判所の判断が本年4月に下されました。判決の内容は「入社時に職種限定の合意があった場合、使用者は労働者の同意なしに配置転換は認められない」というものでした。
配置転換を巡る、この事件での裁判所の判断は下記のとおりです。
【一審・二審】
入社時に職種限定の合意があったが、解雇を回避するための配置転換には業務上の必要性があった
→ 配転命令は「適法」
【最高裁】
職種限定の合意がある場合、使用者には本人の同意なしに配置転換を命じる権限がない
→ 配転命令は「違法」
運送会社に勤務する乗務員は大半が乗務員として応募し、殆どの場合乗務員以外の業務は想定していません。実質的には「職種限定」の契約となります。
全国の労働局に寄せられる労働紛争の中にも、「出向、配置転換」を巡るトラブルは数多くあります。国はこうした状況を踏まえ、今年の4月以降、就労条件を明確にするために使用者側は全ての労働者に対し「就業場所」や「業務内容」の変更範囲を労働条件通知書などに明示することを義務付けました。
最高裁判所が、「職種限定で採用した労働者の同意がない配置転換命令は認められない」と明確にしたことで、将来的に職種間の異動の可能性がある場合は、入社時に変更の可能性をはっきりと明示する必要があります。
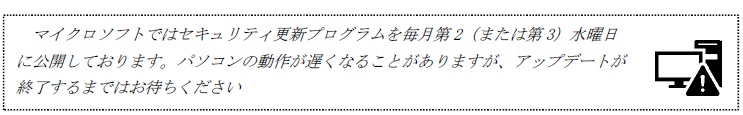
※本内容を無断で転載することを禁じます。

